「退職手続きをスムーズに進めたい」
「退職手続きの準備でバタバタしたくない…」
仕事を辞める際に避けられないのが「退職手続き」です。抜けもれなく順調に進めていきたいけれど、どんな手順で何が必要なのかと悩んでいる方も多いでしょう。
そこで今回は退職手続きについて、チェックリストを交えながら、流れや受け取るもの、返却する物について説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください!
3か月前から始める退職手続きの5つのステップ

どんな流れで退職手続きが進んでいくのかを、ざっくりと確認していきましょう。以下の5つの流れに沿って、紹介していきます。
- 1~3か月前:退職することを勤務先に伝える
- 2週間~1ヶ月:退職届の作成・提出
- 2週間前:引継ぎ・あいさつ回りをする
- 当日:最終出勤
- 退職後:転職先に提出するもの
1.1~3か月前:退職することを勤務先に伝える
退職の意向が決まったら、勤務先にその旨を伝えます。正社員の場合は基本的に就業規則に沿って、定められた期間内に報告しましょう。
一般的には1~3か月前に報告すると、会社側は人員補充や引継ぎの対応ができるので、配慮があると言えます。
退職の報告は直属の上司にしましょう。同僚・先輩に相談すると思わぬルートで上司に伝わり、トラブルに発展する恐れがあるので、対面で行うのがおすすめです。
2.2週間~1ヶ月:退職届の作成・提出
退職届の作成時に、まず確認するべきことは就業規則です。
提出する期限が記載されているためで、中には退職希望日の2か月前までに提出する決まりのある会社もあるので、確認しましょう。
退職届を出すタイミングは、日程が決まったあとに出すのが良く、円滑に手続きが進みます。
3.2週間前:引継ぎ・あいさつ回りをする
意思を伝え退職届が受理された後、早めに引継ぎを行いましょう。後任の担当者がすぐに決まらないことも考えられるので、円滑に引継ぎをするべく業務内容・顧客リストを資料にまとめます。
担当する仕事の手順や現在の進捗状態をわかりやすく記載し、すぐに引き継ぐようにしましょう。
また取引先への挨拶まわりは会社のマニュアルに沿って行います。後任者をたてて、取引先に紹介できる状態にすると、その後の取引もスムーズに進めることができるでしょう。
取引先に退職理由を聞かれても、はっきりとは伝えずに「一身上の都合」などの表現にとどめます。
4.当日:最終出勤
退職当日には社内でお世話になった方や、関係者に挨拶をします。対面または直接挨拶できない場合にはメールで行いましょう。
また会社で借りていた貸与物の返却や、退職後の手続きに必要な書類を受け取るなど、事務的な手続きも一緒に行います。
5.退職後:転職先に提出する6つの書類
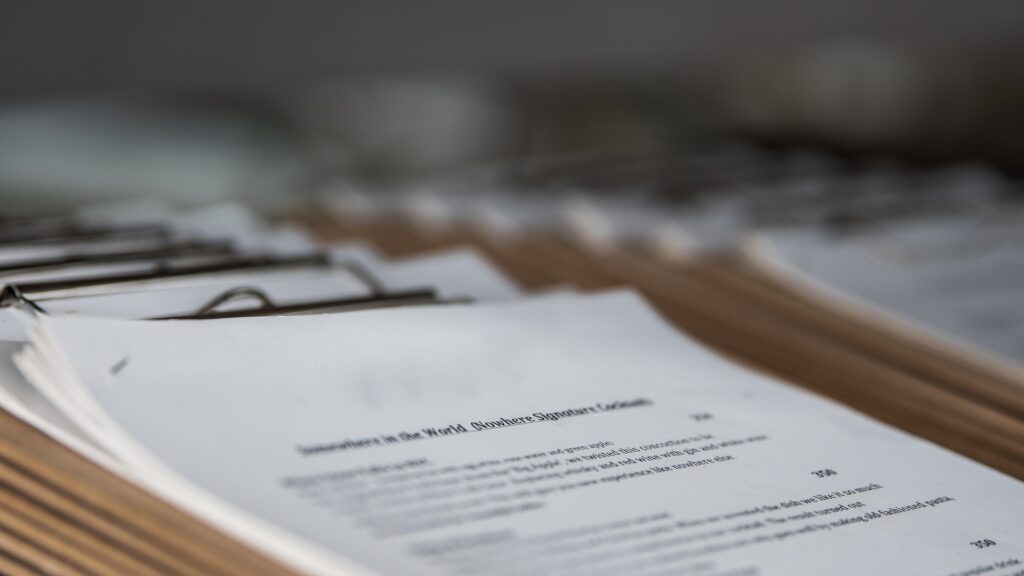
転職先でも事務的な手続きが発生し、書類を提出しなければなりません。退職する際に下記の書類を受け取ったかをチェックしましょう。
- 年金手帳
年金加入手続きのために必要です。退職した会社から受け取った年金手帳は、そのまま転職先に提出します。 - 雇用保険被保険者証
会社から発行されていて、雇用保険加入手続きに必要です。もし紛失した場合はハローワークで発行できますが、時間がかかることがあるので、必要な場合は早めに申請しましょう。 - 源泉徴収票
確定申告や年末調整の際に不可欠な書類です。多くの会社では従業員が退職したのちに源泉徴収票を発行します。入社日に提出を求められていて、用意できないと判断した場合は、早めに転職先に伝えましょう。 - 給与振込先届出書
転職先から給与の振り込み先を伝える書類です。口座の記入と捺印が必要になるので、用意しておきましょう。 - 扶養控除等申告書
扶養家族の有無に関わらず、年末調整の対象者に必須な書類です。 - 健康保険被扶養者異動届(扶養家族がいる人のみ)
扶養家族がいる場合に提出をします。フォーマットが会社で用意されることもあれば、申告書を渡される場合もあり、会社によって対応が違うので必ず確認しましょう。
退職までに1~3か月かかる!?すぐに退職できない!

退職届を提出してから退職するまでに1~3か月必要です。
意思を伝えてから事務的な手続き、人員の補充もあるためです。退職確定後は引継ぎのための資料作成や挨拶まわりを済ませて、退職後も会社の取引がスムーズに進むように配慮します。
諸事情により最短でやめたい場合でも、2週間以内に会社と合意していなければ、退職することは難しいでしょう。
退職手続きで返却すべき3つのカテゴリ
退職の時に会社から借りていたものを返却しなければなりません。そこで返却物について事前に確認しましょう。大きく下記3つのカテゴリにわかれます。
- 健康保険被保険者証(保険証)
- 会社の貸与物
- 資料・マニュアル
1.健康保険被保険者証(保険証)
退職後には無効になるので返却を行いましょう。家族がいる方は配偶者と子供などの扶養家族分をまとめて返します。有給で手渡し出来ない場合は郵送しましょう。
次の保険証が発行されるまで病院では全額負担になるので、受信する際には多めにお金を持っていきましょう。
2.会社の貸与物
基本的に会社の貸与物は退職日までに手渡しで行うのがマナーです。
しかし「退職日まで使用するから当日返却できない」「退職日に返し忘れた」などの理由で返せないこともあるでしょう。
その場合はわかった時点で、早めに会社に連絡し、対応しましょう。
- PC・タブレット
- 携帯電話
- 通勤定期券
- 筆記用具
- 書籍等
- 名刺
- 制服・作業着
制服は当日にも使う場合があるので、返却を忘れやすいです。
返却しないと損害賠償責任を負う可能性がありますので、返さずに放置するのはやめましょう。
「綺麗にして返却してください」と言われていない場合でも、クリーニングして返却すれば問題ありません。 - 社員証
- カードキー
- 社章
出社最終日に返却ですが、探しても見つからない場合は、所属する会社に報告しましょう。始末書と社章料金を支払う形で対応している企業が多いです。
3.資料・マニュアル
貸与物のほかにも資料やマニュアルもすべて返却します。特に個人情報や機密情報が記載されている書類は情報漏洩につながり、トラブルになりかねないため早めに対応するのが良いでしょう。
- データ
- 契約書
- パスワード
退職手続き時に受け取る5つの書類をチェック!
退職の際に受け取る書類があります。転職先の手続きで必要になるので、チェックしましょう。
- 1.雇用保険被保険者離職票(離職票)
- 2.雇用保険被保険者証
- 3.退職証明書
- 4.源泉徴収票
- 5.年金手帳
1.雇用保険被保険者離職票(離職票)
雇用保険被保険者離職票は離職の表明になります。
退職する人が失業給付の受け取りの際に必要になる書類なので、受け取ったのか確認しましょう。
公的文書で発行が義務づけられています。紛失また前の職場でもらえなかった場合はハローワークで発行して、受け取ることが可能です。
2.雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していることの証明になります。基本的には会社で保管されているため、退職する際には必ず受け取るようにしてください。
もし紛失してしまった場合は、雇用保険被保険者番号がわかれば、ハローワークで発行することができます。
番号を知りたい場合は前職の勤務先に番号を聞くか、離職票を持っている場合は記載されているので確認しましょう。
3.退職証明書
必要に応じて受け取るようにしましょう。勤めていた企業から退職した事実を証明するもので、企業に発行してもらいます。
離職票と退職証明書では退職証明書の方が発行が遅いことが多いです。早めに手続きを進めたければ、離職票を受け取りましょう。私的文書で発行に義務はないので発行されない場合もあります。
4.源泉徴収票
前職の会社で発行されるものです。記載されている内容は年間の給与額と支払った税額で、企業は退職の1か月以内に付与する義務があります。
転職先で年末調整をしない場合や年内に再就職をしない時に、翌年の確定申告(3月)の際に不可欠です。
紛失してしまった場合は、前の職場に伝えて発行してもらい、大切に保管しましょう。
参考:国税庁
5.年金手帳
公的年金制度に加入している証明です。年金手帳も退職時に会社から受け取り、転職先に提出する必要があります。場合によってはコピーして提出を求められることがあるので、確認しましょう。
年金手帳は2022年4月に廃止され、年金手帳から基礎年金番号通知書に変わりました。なので年金手帳が再発行できない可能性もあります。
その時には日本年金機構に問い合わせて、先ほどの基礎年金番号通知書を発行してもらいましょう。
退職後に行いたい5つの手続き

前職での退職が滞りなく済んだあとも、必要な手続きがあります。それは転職先での手続きです。
書類を集めて転職先に提出するので、そこまで難しくありません。提出すべき書類が揃っているか確認しましょう。
- 失業給付
- 健康保険
- 年金
- 住民税
- 所得税
1.失業給付
失業中に求職活動している間の生活をサポートしてくれる給付ですが、転職先が決まっている場合には必要ありません。
しかし転職先が決まっていない方は、失業給付の手続きや書類の提出をハローワークで行います。
退職後10日~2週間程度で離職票が届くため、ハローワークに持ち込み、求職の申込を行うことが可能です。
この際に職員と話し合い、受給資格が決定。7日間の待機期間の後に、雇用保険受給説明会に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取ります。
初回の認定日は受給資格から4週間後なので、指定された日に必ずハローワークに行き、失業認定を受けましょう。
2.健康保険
転職または次の企業に入る場合は、会社の指定する健康保険に入るのが一般的です。
しかしすぐに働けないとなると、国民健康保険への加入が必要になります。
個人で加入するか、勤務している家族の扶養に入るかなど検討しましょう。
3.年金
すぐ転職する場合は厚生年金に入りますが、次の就職まで1ヶ月以上期間が空く場合は、国民年金に入りましょう。
手続き出来る場所は住所地の市区役所または町村役場です。手続きを進めることができるのは、本人か世帯主に限ります。
役場で必要な持ち物は忘れずに持っていきましょう。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 離職票などの退職年月日がわかるもの
- 扶養などの配偶者がいる人は、配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(免許証など)
退職の翌日から14日以内に、役場で手続きをする必要があるので、忘れないうちに進めましょう。
4.住民税
退職日によって決まります。1~5月は給与から一括天引きされます。6~12月は普通徴収で一括または分割で払います。
転職先が決まっている場合は普通徴収から、特別徴収(給与からの天引き)に切り替えが可能です。
払い方は納付書に指定された金融機関の窓口やコンビニエンスストア、役場の窓口などで原則、現金として振り込みます。
5.所得税
1年間の全ての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される金額です。
同年中に再就職する場合は前職の源泉徴収票を再就職先に提出して年末調整を行います。
同年内に再就職しない場合は、退職時に源泉徴収票を発行してもらい、確定申告をするべきです。
退職時に確認したいチェックリスト3つ紹介!
退職手続きに関しては返却すべき物、受け取る書類が多岐にわたります。
退職前・退職後に焦ることなく、丁寧に進められるようにチェックリストで確認しながら進めていきましょう。大きく3つをカテゴリでまとめましたので、是非ご覧ください。
- 返却物
- 受け取る書類
- 転職先で提出する書類
1.返却物のチェックリスト
会社に返すものの確認をします。細かなものや重要なものも多いため、一つ一つ丁寧に確認していきましょう。
- 健康保険被保険者証(保険証)
- 会社の貸与物
- PC・タブレット
- 携帯電話
- 通勤定期券
- 筆記用具
- 書籍等
- 名刺
- 制服・作業着
- 社員証
- カードキー
- 社章
- 資料・マニュアル
- データ
- 契約書
- パスワード
2.受け取る書類のチェックリスト
会社から受け取るものです。すべて必要な書類なので、きちんと受け取ったのかチェックしましょう。
- 雇用保険被保険者離職票(離職票)
- 雇用保険被保険者証
- 退職証明書
- 源泉徴収票
- 年金手帳
3.転職する先で提出する書類のチェックリスト
転職した当日は焦らないためにも事前に準備して、万全な状態でいたいですよね。あらかじめ何が必須なのか目を通しましょう!
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者
- 給与振込先届出書
- 健康保険被扶養者異動届
- 扶養控除等申告書
まとめ

退職願を提出してから退職するまでに1~3か月間かかります。引き継ぎや挨拶まわりが必要なため短期間で退職することは難しいです。
段階を踏んで、準備を進めていれば難しくないので、チェックしながら抜け漏れのない円満な退職を目指しましょう!



コメント